

喰っちゃあいかんのか? へようこそ!
今日の食材は 「イラ」です。
イラはスズキ目ベラ科イラ属の魚。
いやあ、このブログの中ではやっとお盆が過ぎた頃さ。
無論、2013年のお話。
今回のイラはもらい物。
パートⅡのタカノハダイ同様、職場の同僚からの贈り物だ。
「この魚、くっちくれろ・・・・」
「ええのんか?こげな魚もろうちも?」
「はやぁ~あんりがたいのぉ。」
と、言う事で遠慮なくいただく。
このイラは職場付近の海に潜って突いたのだとか。
よく見ると、ほおの辺りに刺し傷がある。

この、イラという魚、あまり珍重されない。
まあ、概ねベラの仲間はそんな扱いが多い。
このイラもベラの仲間なのだ。
しかし、なかなか大きい。
1kgは十分にあるね。
さあ、早速観察しましょうかね?
何?いらない?
なんじゃと!?
観察しないなら、ここから先は読んではいかんっ!!
何?じゃあ読まない?
そ、そ、そんなぁ・・・・んごっ!
いいんだ、いいんだ、さいおなら。
ウキッ!
何?いいから、先に進め?
うむ、そうしよう。
はい、背鰭。
カラフルだねぇ。

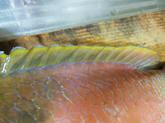
はい尾鰭。

はい、尻鰭。

はい、腹鰭。
鮮やかな黄色だ。

はい、胸鰭。

はい、おでこ。
ふよぷよです。
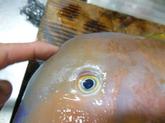
はい、口元。
ちょっと幼い中学生の女の子の頬みたい。

そして、口。
尖った歯が飛び出します。

歯の様子。
なんか、かなり本数少ない。


さて、お楽しみ頂きましたか?
ん?なになに?ふんふん・・・
へぇ~、そうなの?
まさかねぇ、そうかぁ。
まあ、そんな事もあるわなぁ。
うんうん。
で、ウロコを落とします。
大き目なウロコだが、別にはがしにくくは無い。

頭を落とし、内臓を抜き、キレイに洗う。

3枚におろす。
身はキレイな白身ですね。

腹骨をすき、皮を引きます。


体側の骨を切り出し、切りつければ完成。
いやあ、出来ました。

どんなお味なのでしょう?
さっそくいただくのら。
いっただっきもあ~すぅ!!
もんぐもんぐ・・・もんぐ・・・・
あまり味わいを感じない。
年のせいだろうか?
いや、亜鉛不足か?
そんなこたぁ無いな。
なんか、プレーンな感じ。
無垢な素材的な味わい。
変にクセがある訳でも何でもない。
こりゃあ、シンプルな刺身より、何か手を加える必要があるね。
飲食店でそのまま出されたら、きっと”イラッ”っとしますよ。
”イラッ”っと・・・・・
おいっ、こらっ、笑え・・・・
ウキッ!!
QRコード

最近の投稿
最近のコメント
- キツネダイの刺身 に latesjp より
- キツネダイの刺身 に ヒロ より
- 8月後半の大月町産オオモンハタとカサゴのライトな酢〆の握り に latesjp より
- 8月後半の大月町産オオモンハタとカサゴのライトな酢〆の握り に 機械のアッシュ より
- 松田川 産晩秋のヒラスズキのお造り他 に latesjp より
アーカイブ
- 2025年11月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (5)
- 2024年12月 (5)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (5)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (11)
- 2024年7月 (4)
- 2024年3月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年4月 (1)
- 2023年3月 (1)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (1)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (2)
- 2021年9月 (3)
- 2021年8月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (1)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (1)
- 2018年9月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (2)
- 2017年8月 (4)
- 2017年7月 (2)
- 2017年6月 (5)
- 2017年5月 (3)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (7)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (3)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (4)
- 2016年7月 (7)
- 2016年6月 (8)
- 2016年5月 (11)
- 2016年4月 (4)
- 2016年3月 (5)
- 2016年2月 (19)
- 2016年1月 (15)
- 2015年12月 (6)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (4)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (4)
- 2015年6月 (10)
- 2015年5月 (20)
- 2015年4月 (12)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (5)
- 2014年12月 (13)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (6)
- 2014年9月 (12)
- 2014年8月 (16)
- 2014年7月 (5)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (7)
- 2014年4月 (6)
- 2014年3月 (9)
- 2014年2月 (6)
- 2014年1月 (12)
- 2013年12月 (10)
- 2013年11月 (7)
- 2013年10月 (11)
- 2013年9月 (2)
- 2013年8月 (1)
- 2013年7月 (4)
- 2013年6月 (2)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (3)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (6)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (10)
- 2012年10月 (5)
- 2012年9月 (2)
- 2012年8月 (8)
- 2012年7月 (7)
- 2012年6月 (7)
- 2012年5月 (6)
- 2012年4月 (6)
- 2012年3月 (10)
- 2012年2月 (14)
- 2012年1月 (12)
- 2011年12月 (9)
- 2011年11月 (8)
- 2011年10月 (4)
- 2011年9月 (3)
- 2011年8月 (8)
- 2011年7月 (11)
- 2011年6月 (5)
- 2011年5月 (17)
- 2011年4月 (20)
- 2011年3月 (14)
- 2011年2月 (7)
- 2011年1月 (14)
- 2010年12月 (9)
- 2010年11月 (10)
- 2010年10月 (15)
- 2010年9月 (5)
- 2010年8月 (13)
- 2010年7月 (20)
- 2010年6月 (6)
- 2010年5月 (14)
- 2010年4月 (16)
- 2010年3月 (6)
- 2010年2月 (11)
- 2010年1月 (10)
- 2009年12月 (8)
- 2009年11月 (6)
- 2009年10月 (3)
- 2009年9月 (16)
- 2009年8月 (2)
- 2009年7月 (5)
- 2009年6月 (11)
- 2009年5月 (5)
- 2009年4月 (6)
- 2009年3月 (12)
- 2009年2月 (7)
- 2009年1月 (12)
- 2008年12月 (7)
- 2008年11月 (10)
- 2008年10月 (12)
- 2008年9月 (8)
- 2008年8月 (5)
- 2008年7月 (7)
- 2008年6月 (5)
- 2008年5月 (5)
- 2008年4月 (7)
- 2008年3月 (12)
- 2008年2月 (9)
- 2008年1月 (4)
- 2007年12月 (8)
- 2007年11月 (5)
- 2007年10月 (4)
- 2007年9月 (12)
- 2007年8月 (11)
- 2007年7月 (9)
- 2007年6月 (15)
カテゴリー
- その他
- アイゴ科
- アイナメ科
- アオサ科
- アオメエソ科
- アカイカ科
- アカエイ科
- アカメ科
- アジ科
- アナゴ科
- アユ科
- アンコウ科
- イカナゴ科
- イガイ科
- イサキ科
- イスズミ科
- イタボガキ科
- イタヤガイ科
- イトヨリダイ科
- イネ科
- イノシシ科
- イボダイ科
- ウシケノリ科
- ウシノシタ科
- ウツボ科
- ウナギ科
- ウミタナゴ科
- ウミヘビ科
- エソ科
- エゾバイ科
- オニオコゼ科
- カクレイト科
- カゴカキダイ科
- カタクチイワシ科
- カマス科
- カレイ科
- カワアナゴ科
- カワハギ科
- キス科
- キヌマトイガイ科
- キュウリウオ科
- キントキダイ科
- ギギ科
- クボガイ科
- クリガニ科
- クルマエビ科
- ケセンガニ科
- コイ科
- コウイカ科
- コチ科
- コバンザメ科
- コンブ科
- ゴンズイ科
- サケ科
- サバ科
- サヨリ科
- サンマ科
- シカクナマコ科
- シジミ科
- ショウガ科
- スズキ科
- スズメダイ科
- スッポン科
- セミホウボウ科
- タイワンドジョウ科
- タイ科
- タカノハダイ科
- タカベ科
- タチウオ科
- タニシ科
- タラバエビ科
- タラ科
- ダツ科
- ダンゴウオ科
- チガイソ科
- チゴダラ科
- テナガエビ科
- テンジクダイ科
- トウゴロウイワシ科
- トビウオ科
- トラギス科
- ドチザメ科
- ドンコ科
- ナガマツモ目
- ナマズ科
- ニギス科
- ニザダイ科
- ニシキウズガイ科
- ニシン科
- ニベ科
- ヌマエビ科
- ネズミザメ科
- ハゼ科
- ハタハタ科
- ハタンポ科
- ハタ科
- ハナダイ科
- ハボウキガイ科
- ハモ科
- ハリセンボン科
- バカガイ科
- バラ科
- ヒメジ科
- ヒラメ科
- ヒレナガカサゴ科
- フエダイ科
- フエフキダイ科
- フジツボ科
- ブダイ科
- ベラ科
- ホウボウ科
- ホンダワラ科
- ボラ科
- マカジキ科
- マダコ科
- マトウダイ科
- マナガツオ科
- マボヤ科
- マルスダレガイ科
- マンジュウダイ科
- ミミガイ科
- ムツ科
- メカジキ科
- メジナ科
- メバル科
- モクズガニ科
- ヤガラ科
- ヤリイカ科
- ヨメガカサガイ科
- ワタリガニ科
- 喰っちゃあいかのか?:アカヤガラ
- 喰っちゃあいかのか?:エソ
- 喰っちゃあいかのか?:カジカ
- 喰っちゃあいかのか?:カンパチ
- 喰っちゃあいかのか?:タケノコメバル
- 喰っちゃあいかのか?:ニザダイ
- 喰っちゃあいかのか?:ハタ
- 喰っちゃあいかのか?:ハタンポ
- 喰っちゃあいかのか?:フエフキダイ
- 喰っちゃあいかのか?:ホッケ
- 喰っちゃあいかのか?:マゴチ
- 喰っちゃあいかのか?:メダイ
- 喰っちゃあいかんのか?:カサゴ
- 喰っちゃあいかんのか?:タカサゴ
- 喰っちゃあいかんのか?:ハチビキ
- 喰っちゃあいかんのか?:ヒラメ
- 喰っちゃあいかんのか?:ヘダイ
- 喰っちゃあいかんのか?:かつお
- 喰っちゃあいかんのか?:その他
- 喰っちゃあいかんのか?:なまず
- 喰っちゃあいかんのか?:アジ
- 喰っちゃあいかんのか?:アナゴ
- 喰っちゃあいかんのか?:イカ
- 喰っちゃあいかんのか?:イサキ
- 喰っちゃあいかんのか?:イシダイ
- 喰っちゃあいかんのか?:イスズミ
- 喰っちゃあいかんのか?:イワシ
- 喰っちゃあいかんのか?:ウグイ
- 喰っちゃあいかんのか?:ウツボ
- 喰っちゃあいかんのか?:ウナギ
- 喰っちゃあいかんのか?:エイ
- 喰っちゃあいかんのか?:オヤビッチャ
- 喰っちゃあいかんのか?:カマス
- 喰っちゃあいかんのか?:カワハギ
- 喰っちゃあいかんのか?:キビナゴ
- 喰っちゃあいかんのか?:キントキダイ
- 喰っちゃあいかんのか?:クロサギ
- 喰っちゃあいかんのか?:クロダイ属
- 喰っちゃあいかんのか?:コイ
- 喰っちゃあいかんのか?:コノシロ
- 喰っちゃあいかんのか?:コロダイ
- 喰っちゃあいかんのか?:サバ
- 喰っちゃあいかんのか?:シイラ
- 喰っちゃあいかんのか?:シカ
- 喰っちゃあいかんのか?:スズキ
- 喰っちゃあいかんのか?:タコ
- 喰っちゃあいかんのか?:ヒラスズキ
- 喰っちゃあいかんのか?:フグ
- 喰っちゃあいかんのか?:ブダイ
- 喰っちゃあいかんのか?:ベラ
- 喰っちゃあいかんのか?:ボラ
- 喰っちゃあいかんのか?:マグロ
- 喰っちゃあいかんのか?:マダイ
- 喰っちゃあいかんのか?:メジナ
- 果物
- 畜肉
- 発酵食品
- 野菜
- 麺類

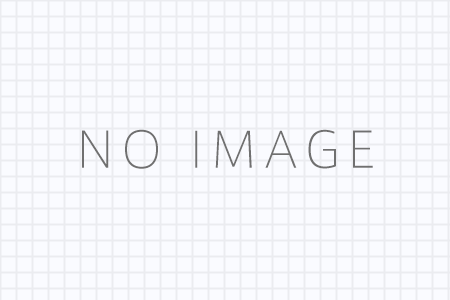





コメントを残す