

喰っちゃあいかんのか? へようこそ!
今日の食材は 「コイ」です。
コイは、コイ目コイ科の魚。
コイは日本各地に生息しています。
比較的汚染にも強く、コ汚い河川にもおりますです。
そんな身近なコイですが、その分布は移植によるものらしい。
琵琶湖など、ごく一部のコイのみ自然分布だとかなんとか・・・
テレビでやってた。
意外と奥深いんだなん。
コイは、肝吸虫の中間宿主となっており、生食は危険なのら。
さすがのおいらも生食しない。
ネット上の情報?を見ていると、養殖のコイは大丈夫だとの書き込みが多い。
果たして、そうなのだろうか?
コイヘルペスが蔓延した際に、霞ヶ浦のコイ養殖現場の映像があったが、霞ヶ浦の一部に網を張って、その中で養殖を行っていた。
自然環境と隔離されているとは言えない環境。
基本的に養殖用飼料を与えているから、野生のコイと比べれば通常の食物連鎖から切れているようにも思える。
しかし、給餌飼料以外、一切口に出来ない訳では無い。
肝吸虫に感染している可能性は否定できないと個人的に思う。
調査した訳では無いから、あくまで個人的意見だ。
もっとも、業界的にはしてほしく無いだろう。
多くのサンプル調査で寄生虫感染が0だったら、安全性を全面にだしてアピールできる。
しかし、その逆だったら?
だから、今後も調査される事は無いだろう。
飲食店であっても、淡水魚の生食は自己責任さ。
最終的には、確率的な話になろう。
ちょっと古そうな?資料ですが、こんなものがあったので、参考までに。
http://www.kiseichu.org/Documents/J2-12-392.pdf
さて、そんなコイちゃん。
一般にドロ臭い個体が多い。
無論、生息環境によります。
ドロ臭くないコイは結構おいしいのだ。
だから、おいらは喰う為にコイを釣りに行きます。
今回は4月に行ってみた。
他の釣りとの調整上、この時期になっちゃった。
産卵期ではないか。
この時期のコイちゃんは岸際でバシャバシャやってる。

そう、やっているのら。
いやん ♡
だから、おいしそうなエサを放りこんでも見向きもしない。
だから釣れない・・・・
ん?誰じゃ、腕が悪いと言うヤツは・・・
その通りじゃ。
うっほんっ!
しかし、神様がおいらにコイを食べなさいと言ってくれたの。
え?ほんとに喰っちもいいのんか?
と、言う事で何とコイに針が引っ掛かったのら。
無論、口では無いボディに・・・・
そして、何とか食材をGET!
やったね。

1匹で十分さ。
さあ、コイを捌こう!
持ち帰ったコイは、まだ生きています。

淡水魚は活けが原則。
今回も無事に活けで調達できた。
ちょっと、サイズがデカイが・・・・
サイズを選べないのが釣獲スタイル。

今回は甘酢あんかけにしよう。
無論、このクソでかいコイを丸揚げにする訳ではござらん。
まずは、ウロコを落とす。
今回は包丁でそぎ落としました。

難しくは無いですよん。
やってみてごらん。
頭を落とし、お腹を開けます。
お腹の中は発達した卵巣。

産卵期ですもん。
コイツも頂きます。
内臓を抜き、キレイに洗います。

3枚におろし・・・・


腹骨をすきます。

で、皮を引きます。

コイ独特の身肉と血合いの色合いですな。
骨が気にならないように薄めにそぎ切るか?

コイがでかいせいもあって、骨も太い。
ちなみに、コイは身肉中にY字状の骨が埋もれております。
これさえ無ければ・・・・・
いっそ、抜いちゃうか?
そぎ切った後なら抜けるべ?
で、抜いてみた。
・・・・やるんじゃねかった。
異常に時間が掛かる。
やりかけた限りはやりましたよワタクシ。
えらいべ?
だれか褒めち。
出来れば、カワイイお姉ちゃんに褒めちほちいな♪
ついでに、各部位も適当にぶった切っておいた。


さて、揚げる準備をしながら、あんかけの準備をしよう。
もらったタケノコ。

ニンジン、タマネギ。


そして長ネギ・・の青い部分。

白い部分は白髪ネギにして使用。
ニンジンは下ゆでしとくか。

で、適当に炒める。
その後、甘酢を投入し馴染ませる。

調味料は、酢、砂糖、醤油、鶏がらスープ。
最後に水溶き片栗粉。
風味付けにゴマ油をちょっち加える。
無論、画像などはないっ。
ごめんなちゃうぃ~~~~~~!!!
ウキッ!
昔、鶏がらスープが無かったので、本だしを使った事がある。
失敗だった・・・・
決して甘酢あんかけに本だしを使わないように・・・
へ?言われなくても使わない?
な、なんじゃと?
おいらがまるでアホみたいじゃないかっ!
おいらはアホでは無いぞ。
永遠の好青年なのら。
さて、コイを揚げていきましょうかね。
片栗粉をまぶして揚げていきます。

ついでに、ヒレやら、皮やら、カマの部分などを揚げる。


肉片が揚がったら、皿に盛り・・


甘酢あんをかける。
白髪ネギをのせ、庭に生えてる三つ葉をのせてみた。


完成だっ!
他の唐揚げもあるど。
今回は下味無しなので、塩かポン酢で頂くのら。


そ、それでは・・・・
甘酢あんかけから・・・頂きますっ。
もんぐもんぐ・・・もんぐ・・・
ちと硬いな。
薄切りにしたもんで、水分飛び過ぎ。
ちょっち失敗か?
しかし、味に問題は無い。
おいちい。
して、ヒレの唐揚げ・・・
ポリポリ・・・

んまいっ!
文句なしっ。
で、周辺部位の唐揚げ・・・
もんぐもんぐ・・・

お、おいちいっ!
カマの部分とか非常においちい。
しかし、皮は・・・・
揚げ時間が短かったな。
ねちょねちょする。
しっかり水分を飛ばさないとダメだね。
はぁ~、んまいにゃん。
誰じゃ?コイは不味いと言うヤツは。
そりゃあ、調達環境と調理の腕が悪いからじゃ。
んごっ!

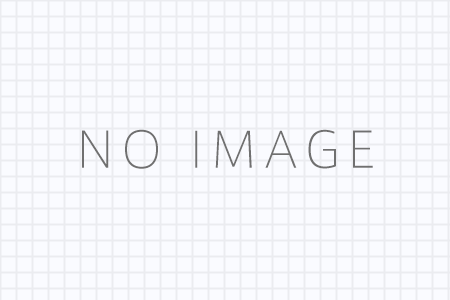






コメントを残す